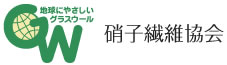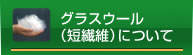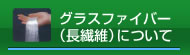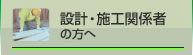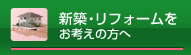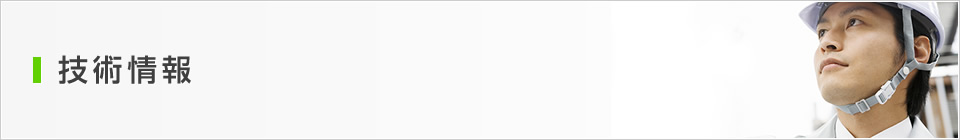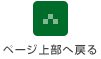第9回定期会議報告
欧州断熱材製造業者協会(EURIMA)との第9回定期会議報告
硝子繊維協会環境委員会は、平成15年11月19日~20日に沖縄県那覇市のホテルを会場に、欧州のEURIMA(欧州断熱材製造業者協会)と硝子繊維協会(GFA)/ロックウール工業会(RWA)との第9回定期会議を開催。 今回もオブザーバーとして米国のNAIMA(北米断熱材製造業者協会)代表が参加しました。
●日 程:平成15年11月19日(水)~20日(木)
●場 所:沖縄県那覇市ロワジールホテル
●出席者:(総計:10名)
○ EURIMA(3名)
Mr. H. Biedermann (EURIMA Director General)
Dr. O. Kamstrup (Rockwool International社)
Dr. A. de Reydellet (Saint-Gobain Isover社)
○ 日本代表:硝子繊維協会(GFA)環境委員会(8名)
ロックウール工業会(RWA) 環境委員会(7名)
○ 米国(オブザーバー): NAIMA (1名)
Mr. K. Menzer (NAIMA President and CEO)
○ 通訳 (2名)
以下、議事次第にそって、定期会議の要旨をご紹介します。
はじめに EURIMA代表(Biedermann氏)代表挨拶主旨
・欧州の経済状況は、良い方向への変化はみられないが、東欧の10カ国が新たにEUに加入することで、プラスへの変化を期待している。それを受けて欧州では東欧諸国を巻きこんだ業界再編成中で、グループ化が進行中である。
・ この会議を含め、国際的な業界の協調ネットワークを強化し、IARCの見直しのように、グローバルな観点から規制に対応していきたい。
・研究科学分野では、IARCが既に人造鉱物繊維への発ガン性分類を変更したことを受けて、欧州連合(EU)が2004年には皮膚刺激性分類(irritant classification -R38)でミネラルウールの評価変更を決定したことなどから低調になっているが、2001年以降の最新の状況について報告したい。
1. 業界活動報告(Report on Industry Activities)
最新の協会組織、業界統計、一般活動状況について報告
硝子繊維協会(以下GFA)
●鈴木専務理事
トピックスとして、建材からのホルムアルデヒド放散規制に伴うJIS改正対応について、グラスウール販売促進活動としてGWPR委員会設立、外張断熱工法GWOSの普及促進、住宅外壁防火性能研究活動推進のための研究会参加などについて報告した。 2.このような市場にミネラルウールの新規参入企業が有り、厳しい状況にある。
ロックウール工業会(以下GFA)
●田所専務理事
トピックスとして、12月事務所移転について、安全環境活動では、RW天井板施工現場の粉塵測定実施、RW繊維の溶解性評価試験の継続、農業用RWのバインダーフェノール樹脂の分解性評価等について、また長期的テーマとして工業会による一元化リサイクル体制の検討について報告した。
EURIMA
●Biederman氏
1.統計資料まとめについて
欧州では公取法の運用が厳しく再開しなかった(昨年報告では公開資料による再開を計画)。
2.委員会活動報告
a. HSC健康と安全委員会
皮膚刺激性分類(R38)の撤回、有害性廃棄物、論文検索データベース構築、建設作業者の曝露レベル調査等の7プロジェクトに取組み
b. 技術委員会
CEN、ISO、熱、吸音、耐火等の5つのプロジェクトについて取組み
c. 市場委員会(ホームページ更新 … http://www.eurima.org )
市場戦略案の立案、EuroACE* 、ECOFYS**などの関係業務を管掌。
注:*EUの施策に建築物のエネルギー効率アップによる省エネ施策を盛り込む為のPR活動推進のために組織化された欧州建材企業連合。メンバー企業総売上:600億ユーロ(7兆8千億円)、従業員数34万人の一大組織。EUも無視できない団体。
**ECOFYSは、EC委員会が活用する建築環境関係の民間研究調査機関(独)、EURIMAも最近よく活用…ECOFYSレポート1及び?など。
NAIMA
●Mentzer氏
1.組織
・ メンバー13社で構成。グラスウール及びスラグウール(RW)市場の95%を出荷。
・ マーケティング(市場拡大)、総務、規制対応の3グループを10名で担当。
2.トピックス~次の2テーマについて報告あり。
A) 断熱材と公衆衛生:ハーバード大公衆衛生大学院研究報告
a. 既存の戸建住宅を最新の省エネ基準(IEEC2000)に断熱改修することにより、エネルギー消費減少し大気汚染が減少、更に呼吸器系疾患減少し早期死亡が減ることが判明。
b. 新築住宅でも同様の効果を確認。断熱強化によるこれらの結果は非常に大きな政治的なメッセージである。欧州やアジアの市場でも成り立つ筈なので大いに活用願う。
B) 持続可能な開発(Sustainable Development)及び気候変動:
? 持続可能な開発世界頂上会議(WSSD:World Summit on Sustainable Development)では、EURIMAとNASIMAがNGOとして参加を認められ、ミネラルウールがもたらす効果について大きくPR。エネルギー効率と断熱について条約の中に盛り込まれるという多大な成果を得た。
? 健康問題では、IARCの評価見直しの効果を得るための活動に取組中。 EPA, OSHA、カナダなど内外行政機関、公的機関が等級区分などで誤りがあればその修正活動を行う。
? IARC評価見直しでは、日,北米,欧,豪,メキシコ,等の国際協力で大きな成果を得た。今後もWHO、ILOへの協力を通じて有意義な活動が期待できる。
? 気候変動抑制でも国際的な協力関係の結果、条約の中で断熱は「CO2削減のクリーンな手段」として記載され、大きな成果を得た。
? 新エネルギー法案を米国議会で現在審議中、成立時にはかなり大きな省エネルギー減税期待。
・ 既存住宅のエネルギー効率改善(断熱改修及び設備導入など)20%達成の場合、上限2000ドルの減税。これにより、約1万ドルの省エネ効果が得られる。
・ 新築及びプレファブ住宅:2000年基準より30%削減では1千ドル、50%削減では2千ドルの減税。
商業ビル:エネルギー使用量50%削減により、1.5ドル/ft2減税
? 米国は京都プロトコルには署名しないが17億ドルの予算でCO2削減の種々の国内プロジェクト:連邦レベル、州法レベル、業界レベル、などに取組み中。何れも断熱強化をサポートする施策。
? 日欧と同様にNAIMAではグリーンビルディング゙についても積極的に取組中。ミネラルウールのグリーンデーターに関する膨大なライブラリーを整備、その他種々のPR活動に取組中。
2. 規制及び等級区分(Regulatory/Classification)
日本代表
●RWA富田氏
1. 労働衛生規制の変更点
◆粉塵許容濃度の計算式がH16年4月より変更される。
◆日本産業衛生学会 の2003年度「作業環境許容濃度指針」変更について
・ GW/RWは、発がん物質から削除
・ GW/RWとしての許容濃度(皮膚刺激が主)として、1f/cm3を提案
2. 環境関係
粉塵許容濃度の計算式がH16年4月より変更される。
・ PRTR法ホルムアルデヒドの届出対象が、含有量が1%以上で生産数量:5t/年→1t/年に強化。
・ 建築基準法改正によるホルムアルデヒド放散建材使用規制(H15年7月より)
・ 2005年までに、VOC放散建材についても規制、試験法JISA1901紹介など
EURIMA代表
●de Reydellet氏
1.溶解性繊維の認証制度(EUCEB)
現在メンバーは26社38工場。内23工場が認定を受。西欧諸国中心、今後東欧諸国増加の見込み。
2.危険物質分類体系について: OECD及びREACH SYSTEM
・ OECD新分類:2003年7月国連の経済社会委員会で、化学物質の分類と表示の国際統一を図るため国際的調和システム「GHS:Global Harmonized System」が採択された。呼吸器官への刺激も含まれるが、GW/RWは適用対象外。
・ EUではOECDの規定に基づき新規定「The REACH System」の検討着手(現行ルールは1967年EC指令による)。現在ある40以上の指令は全てリーチシステムに切り替えられる。
★ REACH(Registration, Evaluation & Authorization of Chemicals)
? 提案理由:旧来の規定では膨大な化学物質から生ずるリスクが捉えきれず、対応も遅いため。
? 従来規定では既存化学物質(10万種以上)は対象外、新規化学物質のみ(約3千種)。
? 当システムでは安全性の立証責務がこれまでの当局から業界へ移行される。
? リーチにはラベリング及び包装に関する規定は含まれないので従来のEC指令規定が残る。
? REACH原案はあまりにも厳しすぎて問題だった。民間企業やNGO、関係諸国などから6000件以上の意見が寄せられた。これらに基づき2.3週間の内に改正案ライトリーチが上提される予定。
? 改正案は、より少ないコストで実施できること、また官僚的でなく実務的な改正案を目指している。
★ Light LEACH
? REACH原案では年間10kg以上の製造物又は輸入品の新化学物質は全て登録対象。ライトリーチでは、年間1t以上に緩和の予定。
? 登録内容:人体及び環境に対するリスクアセスメントについて
? 欧州化学物質庁(European Chemicals Agency以下当局と呼称)を新設。 業務内容:登録管理、データベース管理、守秘データ以外の公開。
? 既存登録物質の80%は特にアクションの必要はない。
? 新システムはまだ草案の段階であり、公式ジャーナル刊行は’07、’08年頃の見込み。
Substance Preparation Articles について
顧客にリスクが想定される場合、ラベリング及び安全な使用方法を含むArticlesを公表しなければならない。
? 上市認可(オーソライゼーション):リスク管理が行われていると判断される場合、当局か上市認可。
? 2つの評価方法について
・ 書類評価:動物実験抑制のため添付資料を評価。日米など他国のメーカーのデータでも可。
・ 物質評価:人体及び環境にリスクをもたらす可能性のある物質について、規制当局が行う。
? 消費者は当局から安全情報の入手が可能となった(リーチ原案では守秘義務上不可)。
? リーチシステムの実施コスト対メリット
・ ライトリーチ直接コスト:23~52億ユーロ(3000-7000億円)…当初案の82%減
・ 人の健康について予想される利益は、30年間で500億ユーロ(6兆5千億円)
3. 皮膚に対する刺激性の欧州分類R38について(Preparation 指令)
・ 専門家の間では廃止の合意が出来ている。EURIMAも要請中。2004年には削除を期待。
米国
●Menzer氏
1. NTP(Federal National Toxicology Program米国毒性プログラム)毒性リストへの対応
? これまでIARC評価に基づきNTPリストにGWが記載されていたが削除を要請している。
⇒ 2004年秋には削除される見込み。
? 2004年NTP削除後は、California州のProposal65からも削除要請することにしている。これはくじ引きで規制対象を選定。偶々ミネラルウールが当たったもので全く科学的根拠がないため、実際には運用されていない。最終的にはIARCにもNTPにもこのような分類はないので、削除される筈である。
2. FTC(連邦取引委員会)断熱性能開示規則
住宅の取引に際して、断熱性能開示を求めるもの。湿式セルロース吹き込み工法に対する乾燥時間の明示要求などあり、セルロースには不利な規則。
3. カビ(MOLD)
・ 米国では、欠陥建築として訴訟頻発。またリスクマネジメントの問題として大変重要化。
・ ミネラルウールには関係のない問題だが、建物の環境としては重要。
・ 重要な事は、カビと人の疾病との間に医学専門家により相関が認められなかったという点。
4. その他
・ 等級分類など健康に関する世界中のデータベースを整備中。日本からのデーター提供を歓迎する。これまでの資料を参考のために両協会に配布。
3.研究調査報告(Health & Safety/Scientific)他
日本代表
●RWA富田氏
RW吸音天井板施工現場の個人暴露濃度調査結果(詳細略)
EURIMA代表
●Kamustrup氏
IARCの2001年の再評価後は、研究内容が減っている。
a. IOM(Institute of Occupational Medicineスコットランド)委託研究
・ 「ラットの肺における人造ガラス質繊維の滞留と消滅のモデリング」Tran他、2003年
b. 技術委員会
・ 「ラットのMMVF短期吸入毒性評価」Bellman他、2003年
c. 疫学研究
・ 「ロック及びスラッグウール産業に従事していた肺ガン患者における肺ガンリスク調査」、Soldan他、2003年
【結論】
・ 17例について調査。この内16人から石綿繊維(欧州産アンフィポールのトレモナイト)が検出されたがロック及びスラグウール作業者の曝露と肺ガンリスクの間に相関は認められなかった。但し、リサーチャーの結論はまだ出ていない。調査レポートを両協会に渡す。
Qロックウール(RW)、ストーンウール(SW)は見つからなかったのか?
A 肺を調査したとき全例でアスベストが見つかっている。
SW/RWは化学組成上溶解性だから残らない。GWも同じ。
4.省エネ・環境・マーケティング
(Energy/Environment/Marketing)
日本
●GFA松岡氏 詳細略
・ 産官学共同開発の建築物環境評価システム(CASBEE*)の紹介
(*Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency)
・ わが国のこれからの建築行政の重点課題とその中でのCASBEEの位置付けについて説明
・ 欧米の高い関心を引いた。
EURIMA
●Kamstrup氏:3種類の断熱材のLCA比較研究
・ ロックウール社が協力しデンマークの研究機関がFLAX(麻繊維)、紙製ウール(PW:セルロース繊維)、ストーンウール(SW)の3種の代表的メーカーの断熱材を天井に施工した際のLCAについて比較研究を実施、シアトルで開かれたLCAの国際会議で報告した。
【結果】
? FLAXがもっとも環境負荷が高く、悪性肺疾患の危険性がある。
? PWは、再生紙を使用しても85%のバージンペーパーが必要。
? SW(生体内溶解性HTファイバー)の健康影響調査が最も多く安全が確認されている。
? いずれの断熱材も、断熱による環境負荷低減効果が大きい。
・ ECは、FLAXのような再生可能(renewable)原材料の使用を促進するドイツの計画を支持しているが、これらの材料が既存の材料より高価で多くの化石燃料を使うことに注意すべきである。
EURIMA
●deReydellet氏:
参考文献データベース(Biblographic Database)構築
・ MMMF及び有機繊維の健康影響に関する全ての出版物を集めたデータベース検索web。
・ フランスの研究機関であるAPPAが作成管理 http://www.fberes@appa.asso.fr
・ 現在助成金はEURIMAが負担しているが、NAIMA,FARIMAも参加の予定。
・ 現在は検索と要旨のみだが、オンラインで全文を入手できるよう改善する。
・ 年間費用:26,000ユーロ(340万円)~分担すれば日本の参加を歓迎する。
日本
●GFA神谷氏:販売促進用CD-ROM「The EARTH」の紹介(内容省略)
・ 防火編を上映したところ欧米の関心高く全員がCD-ROMを要求した。
・ NAIMAでも火災テスト実施した。資料を後で送る。
5.国際活動報告(Report on International Activity)
EURIMA
●Biederman氏
a. 防火編を上映したところ欧米の関心高く全員がCD-ROMを要求した。
IARCの評価変更に基づきILO Code of Practice の見直し。ミネラルウール2Bから3に訂正(内容変更はなし)を要請する。
b. NAIMAでも火災テスト実施した。資料を後で送る。
・ EUの新エネルギー効率法:2002/91/EC「建築物のエネルギーパフォーマンス」は’06年初施行に向けて各国での法制化支援実施中。
・ この指令を基にEURIMAではCO2削減効果についてECOFYSに委託して種々試算を実施(ECOFYS?報告)。業界にも影響の大きい指令。当指令には欠陥があるとの指摘有り。
c. ECOFYS?~‘03年末刊行予定、1月よりロビー活動に活用の予定。
・ 新法では、1000?以上の新築・改築のみを対象。
・ ECOFYS?では、1000?以下の場合について検討。EC指令と比較実施。
・ まとめ:現行ストックに対して新法の適用の場合11%、200~1000?に拡張すると21%、全ての住宅に拡大すると55%(316千トン)のCO2削減が可能であるという内容。
・ これまでEUではこのような検討は行われていない。住宅の効果、特にリノベーションを実施した住宅の削減効果を忘れてもらっては困るので、今後これをもとにEC当局へ更なる省エネルギー政策の働きかけを行っていきたい。
おわりに EURIMA代表( Biederman氏)の挨拶より
我々の製品がより政治的に魅力的(Sexy)であることを多くの人に伝えるべき時が来ている。忘れてならないのは、我々の製品が解決策(Solution)であって、問題を引き起こすものでないことである。我々のスローガンは、「もっとも持続可能なエネルギーは、省エネルギーである。」(The most sustainable energy is energy saved. It’s more than ever actual.)
★次回予定:ウイーンにて 2004年11月3日~4日