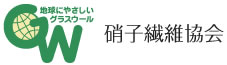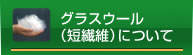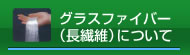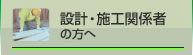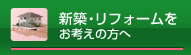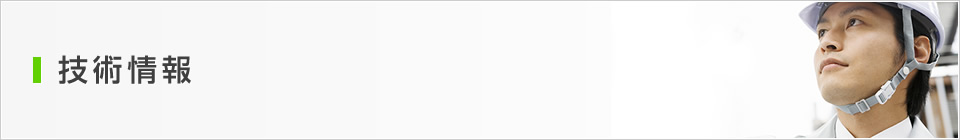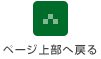第8回定期会議報告
第8回定期会議内容報告
平成14年11月14日〜15日に
欧州断熱材製造業者協会(EURIMA)との
第8回定期会議を開催いたしました。
硝子繊維協会環境委員会は、ギリシャ国アテネ市のホテルを会場に、欧州のEURIMA(欧州断熱材製造業者協会)と硝子繊維協会(GFA)/ロックウール工業会(RWA)との第8回の定期会議を開催しました。 なお、オブザーバーとして米国のNAIMA(北米断熱材製造業者協会)代表が参加しました。
●日 程:平成14年11月14日(水)~15日(木)
●場 所:ギリシャ国アテネ市
●出席者:(総計:10名)
○ 欧州:EURIMA (3名)
H. ビーダーマン 氏 (EURIMA 専務理事)
O. カムストラップ博士 (ロックウールインターナショナル社)
A. ドライドレ博士 (サンゴバンイソベル社)
○ 日本:硝子繊維協会(GFA)及びロックウール工業会(RWA) の環境委員会代表(各2名)
○ 米国:NAIMA (1名)
K. メンツァー氏 (NAIMA 専務理事)
○ 通訳 (2名)
以下、会議議事次第に沿って、欧米のビジネス情報を中心に要約をご紹介いたします。
欧州断熱材製造業者協会(以下EURIMA)代表挨拶
ビーダーマン氏
1. 欧州のビジネス環境は、昨年の会議以降も改善なく依然状況悪い。価格低下が各国で続いており、各企業は再構築に取組んでいる。オーエンスコーニング社は欧州から完全に撤退した。
2.このような市場にミネラルウールの新規参入企業が有り、厳しい状況にある。
3.EURIMAメンバーにも変化が有り、従来サンゴバングループは各国企業毎に計10社加入していたが パリ本社のみ加入となった。 パリ本社で中央欧州及び東欧州もカバーすることになっている。
4.ボード会議も変更があり、サンゴバンとロックウールインターナショナルの2大グループを中心とした組織になった。
5.今会議で報告するEURIMAの主な活動:
★市場メッセージ開発によるマーケティングへのアプローチについて
・IARC 再評価を受けてのイメージアップ活動
・EU 建築物統一指令とその対応について
・断熱材厚さ強化による省エネ及びエネルギー効率改善促進
・国際協力活動による各国法規制化対応としてのロビー活動について、など
★EU健康安全関係統一指令(発ガン性区分97/69/EC)以降の健康安全面での欧州法規制状況について
・最新の研究調査結果及び規制対応
・新欧州危険物表示制度(New European Classification System) 、などこれらの情報が日本の業界の市場活動に大いに参考になることを期待している。
業界活動報告
EURIMA
●ビーダーマン氏
各委員会活動の中からトピックスを紹介。
■技術委員会:
1. 他材料との種々の比較評価テスト実施中。
2. ミネラルウールが試験ナシでユーロ等級A-2になるようEUに要請中。
3. その他、新規制「Products Standards:危険物指定」 問題に全力で取組み中。
■マーケティング/エネルギー/環境委員会
1. この1年間で新しい戦略プランを開発した。
2. IARCの再評価を受けて、ミネラルウールへの良い印象を構築する為の広報活動に注力中。
3. 統計データー作製中… 独禁法上の問題から4年前に中止していたが、データーの収集方法を改善して再開。来春発表予定。
■EUCEB(European Certification Board)
…生体内溶解性繊維認証機関事務局(EURIMAとは独立組織)
北米断熱材製造業者協会(以下NAIMA )
●メンツァー氏
■ 市場対応のための組織の再構築について
1. 製品グループに、屋内空気品質関係(Air Handling)など新しい業務を追加。
2. 他方既存業務担当併合等による組織の効率化実施。また市場への技術サービス/法規制・基準化対応などを通じて、マーケティング支援業務の効率アップと強化実施中。
■ 活動について
1. 成長分野を特定し、重点的活動実施…:持続性開発(Sustainable Development)、気候変動、連邦/州エネルギー政策、国家安全保障、公衆衛生*、などの関係分野。
注:*断熱強化により、空気汚染改善され死亡率が低減(ハーバード大調査研究報告より)
更に経済効果、社会保険料率ダウン効果も期待。
2. 行政への省エネ・環境・公衆衛生等の面から施策推進に積極的に協力。
3. マーケティング支援活動業務
・米国労働安全衛生局(OSHA)との良好な協力関係継続中
・住宅取引時の正しいR値表示法。(FTC連邦公正取引委員会規定の徹底)
・IARC再評価を受けて、行政のNTP(国家危険物リストプログラム)及びカリフォルニアPR65などの見直しへの協力。
・プレス活用によるミネラルウールイメージアップの為の広報活動 。
EURIMA
●ドレイドレ氏
■ 統一指令(97/69/EC:発ガン性区分)関係
1. 規制除外条項(Nota Q)について
・97年制定時より5年後(2002年)見直しの予定なるも未だ内容未定。
・2003年1月にはECより発表される見込み。
・EURIMA及び各国専門家もECへ継続を要請中。
2. 皮膚への刺激物質指定(Irritancy R38条項)について
・97年制定時には何ら科学的根拠はなく政治的な理由で決定されたもの。
・ 発ガン性規制除外繊維(Nota Q適合品)も含めて、とにかく全て一つのファイバーとして規制しようとしたもの。
・EURIMAの評価試験でも、いかなる炎症反応も発現していない。
・EURIMA では専門家に依頼して、Nota Q 適合品については皮膚刺激物(Irritancy)マーク表示除外を要請中。
3. EUCEBとは、RW/GWを対象に設置されたメーカー24社によるNota Q適合証明マーク表示制度
・現在2社が表示中。2003年度には表示企業大幅に増加見込み。
●カムストラップ 氏
■新欧州危険物表示制度(New European Classification System)
・ECの危険物(Hazardous Substances)に関する新しい表示制度。
・ 2年前から白書で公表されている(ウェブサイトで閲覧可能)。
・米国政府も賛同(メンツア―氏)。
・当制度はOECDが推進中のシステムでもある。
・新システム導入によりどう変わるか…現行vs将来(下表)。
| 現在 | → | 将来 | |
|---|---|---|---|
| 危険物かどうかの判断 | 行政側が行う。 | → | 企業側で判断 |
| 判断の対象物 | 新物質又は10kg以上出荷のもの | → | 全ての上市品が対象 |
| 判断の内容 | 判断の内容 | → | 更にRisk*の判断も追加見込み |
注:*Hazardousとは、物質そのものの危険度(例:炎そのもの)。Riskとは、その物質から離れたときの危険度(例:炎から離れている時) 。
・新システムの影響:現行の発ガン性等級区分等の規制を廃止できるかもしれない。
・EC統一指令告示時期:2002年度末予定だが遅れる見込み。
・施行時期:2005年の見込み。
・OECDが進めるこのシステムは、業界にとって将来非常に有意義であり、重要な問題。⇒これまでと同様に欧米日の3者協力して国際協調で取組むべき。
・次回会議では、大きく取り上げて議論したい(メンツア-氏)。
Q:
1.ミネラルウールの廃棄時、規制があるかどうか?
Ans:
・製造工場からの廃棄物は、非危険物(Non-Hazardous)
・建築現場からの廃棄物は、危険物(Hazardous)[理由]:皮膚刺激物(Irritant)になっているため
・ 但し、国により対応異なる。
アイルランド、フランスは、Non-Hazardous
デンマークは、Hazardous だが、Non-Hazardous 扱い。
・ EURIMAとしては、Non-Hazardousに変更するよう、EUへ要請中。
日本
●RWA富田氏
■ ホルムアルデヒド放散建材規制
・建築基準法改正に伴う居室用ホルムアルデヒド放散建材に対する使用量規制等について紹介。
・まだこれらの法的規制のない欧米側からは、高い関心が示された。
・JISによる放散建材の等級区分規定、室内空気質のホルムアルデヒド濃度と使用量との関係式の説明、チャンバー法による放散速度測定法のISOベース規格番号.等について、後日回答する事になった。
安全衛生/リサーチ(HEALTH AND SAFETY /SCIENTIFIC)
ヨーロッパ
●カムストラップ氏
■ IARCケースリサーチについて
・肺ガン組織中のグラスウール、ロックウールなどミネラル繊維の有無調査。
・リサーチは完了、現在IARCで報告書作成中。
・IARC調査者の話では、ミネラルウールに何ら問題はない。
■ 競合材料について
・政府が健康に良い材料との理由で、過去4年間に年約1億2千万円の予算でセルローズ及び麻繊維(FLAX)のPRを行ってきたが、何ら販売実績は出ていない。
・生産者側は、LCA比較でもミネラル繊維より数十倍優れ、環境に優しいとPR。
・独フランフランホッファー研究所報告では、セルローズは肺内でセラミックスよりも耐久性があるとのこと(アスベストのように生体内で耐久性の高い繊維は発ガン性の懸念がもたれる。)
・更に、吸入法(IH法)で長期滞留による慢性的影響を調査すべしとリコメンドしている。
・綿、FLAXからのダストは、バイシノーシス(BYSSINOSIS:日本では通称綿肺とよばれる職業病、綿繊維肺沈着症)を起こす。
・綿肺(バイシノーシス)は、喘息を起こし死につながる場合も有り。吸入性病気に対し、プラスの影響有りなどの調査報告も有り。
・デンマーク国立労働衛生研究所(AMI )報告。
*セルローズ、FLAXなどの断熱施工では、ミネラル繊維より多くのダストが発生し、グラスウール/ロックウール以外はマスクなどの保護具が必要。
*AMIレポートは現在英訳中。完了次第日本に送るとのこと。
・気管へのセルローズ繊維注入動物実験を行うと、発ガン性を示すという報告が有る。
・セルローズに対し議論が2つ有り。
a) 環境的に良いということに該当しないという反論
b) 生産エネルギーがグラスウール/ロックウールよりも実際は高い、等の反論。
・EURIMAとしては適切な方法で反論根拠を示す。デンマーク政府、ECへも提出。
・EURIMA が1200万円の費用でLCAエネルギー調査委託実施。報告書有り。
*ミネラル繊維 … 21 メガジュール/m2
*セルローズ繊維 … 35 メガジュール/m2
*FLAX … 50 メガジュール/m2
但し、種から、農薬散布、セルローズ繊維製品(ペーパー)製造迄を含む。
日本
●GFA松岡氏
■ 現行グラスウールの生体内溶解性動物実験報告
・硝子繊維協会が産業医科大学に委託してH13年に実施した気管注入実験について報告。
・EU法に準拠して実験実施。
・評価試料:一般グラスウールの硝子繊維協会規格組成2種類
・比較試料:CM44(仏サンゴバンから輸入、欧州で生体内溶解性確認済繊維)
・国内の2種類ともEU指令NotaQに適合 ⇒「生体内溶解性繊維」の評価を得た。
・Interresting!(興味深い!)と大変関心を持って聴講していた。… 繊維がラットの体内で徐々に表面溶解、痩せながら大きく曲がっていく状況、更にはついに繊維に割れが入り折損直前の瞬間をとらえた電子顕微鏡写真などは特に興味深かったようだ。
●GFA八谷氏
■ 断熱材のLCA調査報告
・硝子繊維協会が宇都宮大から入手した、各種断熱材の最新のLCA値について報告。
・発泡系断熱材、セルローズ繊維との比較でグラスウールなどのLCA値の方が小さかった為、ミネラルウールの良いPR材料になると大好評であった。
・今回の資料(英訳版報告書)の電子ファイルが欲しいとの要請が有り、使用データの出典元の了解を得た上で、後日送付することになった。
Q:
・この結果を、欧米でのPRに活用したいということで宇都宮大の今後の
正式論文発表予定について質問が有った。建築学会等で発表を予定さ
れていることを伝えた。
Ans:
・発泡材が現行のフロン系から、炭化水素系、水等に変更された場合のLCA値について強い関心が示された。今後追加調査が必要である。
米国
●メンツアー氏
■ 米国毒物登録局
(ATSDR:Agency for Toxic Substances and Disease Registry )の活動について
・人造ガラス質繊維について毒物学的プロファイルを作成中。
・草稿は、グラスウール、ロックウールにとって有意義な内容になっている。
~アスベストとは別物という証明の記載など。
■ ワールドトレードセンター崩壊後の曝露問題について
・グラスウールがNY市曝露有害物質リストに記載されていた。
・公聴会では、なぜグラスウールが記載されているのか質問があった。
・リストアップは、NTP (米国毒物製品リスト)記載品をそのまま転載したもの。
・NTPリストは国際ガン研究機関(IARC)の評価区分に基づく。⇒ IARC再評価による区分変更で、リスクは大きく減少した。
・従って、今後公聴会の進捗と共にグラススウール粉塵への懸念は解消されるだろう。
■ NAIMA/OSHA(米国労働安全衛生局)協力計画(HSPP)
・職場安全衛生及び曝露のデーター提供面で良好な協力関係にある。
・OSHAに特に新たな規制の動きはない。
・毎年上記データーベースの最新化実施
… 最新版CD-ROM帰国後受領済。
●ビーダーマン氏
■ 国際活動報告
1. EURIMA/NAIMA/FARIMA(欧/米/豪)協力会議
・6ヶ月毎に、3者集まって会合を開いている。
・ISO-TC163(断熱材関係のISO規格作製委員会)対応について
*米国、カナダ、メキシコは、アメリカ材料試験協会規格(ASTM:America Society for Testing and Materials)のISO化で対応。
*欧州は、欧州標準規格(CEN)で対応し、夫々規格作成作業の重複を避けている。
・“COP8:Final Decision in Bonn2002”に対する批准段階にありロシア、カナダの批准待ち … OKだろう。
・グラスウール原料としてのリサイクルガラスカレット使用量と使用比率。
*生産量:年間150万トン~170万トンに対し、使用量:50万トン ⇒ 約30%
*米国では1社が最大50%程度の使用実績は有るが、日本ではグラスウールメーカー各社が80%以上という実績に対して驚嘆していた。
・室内空気質環境について:米国でも結露、カビの問題に関心が高まっている“Dry is Good Pathway”~「乾燥」が最良の解決策。⇒“セルローズはカビが生える”と差別化PRされているとのこと。
省エネ・環境と市場関係(ENERGY/ENVIRONMENT/MARKET)
ヨーロッパ
●ビーダーマン氏
■ ユーロエース活動について
… トッピックス: 建築物統一指令(Building Directive)
・良いメンバーシップを維持しながら、マーケットプロジェクトに取組むことができた。
・炭酸ガス放散量の40~45%は、建築物からの放散が占める。
・家庭からの発生量の70%は、冷暖房用である。商業用ビルでは50%である。
・ユーロエースメンバー企業の製品の内、断熱材分野での炭酸ガス放散削減可能量は2億トンに及び、最大である。
・なぜ、建築物統一指令が出されるのか?⇒建築物は欧州エネルギー使用量の40%を占め、更に増加傾向。
・建築物統一指令による規制方法:
*エネルギーパフォーマンス測定法、検査法、再評価法等の導入。
*大型ビルへはより高い基準適用、新規建築物には改善基準適用など。
・新規制により2010年迄に、欧州炭酸ガス放散削減目標値の21%-4500万トンが削減される見込み。
・これは、現在の欧州の建築物でのエネルギー使用量の22%の削減になる。
・第6条が重要:1000m2以上の既存建築物には最小のエネルギー基準が適用される。
・個人資産である住宅はEU指令対象外だが、100m2以上の住宅も対象にすべきだと主張する動きもある。
a)平均的住宅:50m2~200m2
b)広い住宅:200m2~1000m2 の2グループに分けて主張されている。
・ECが建築・環境関係の調査で良く使用する民間リサーチ機関:エコシス*をEURIMAでも活用し、その調査結果を行政及び市場にPRしている。
・第7条 認証表示規定…公的建物は認証表示必要。
・2002年末に公布予定 … 各国で認証機関必要になる為、若干遅れる可能性あり。
・各国は、公布後3年以内に国内法へ導入しなければならない。
■ 断熱材使用厚さの調査:
・材料に関係なく単純に使用製品厚さを集計したもの。
・科学的な調査ではないが、地域別分布傾向を分かりやすくする事が重要な情報となる。
・調査結果から、北欧に対して、欧州の人口密集地域である南部の断熱材厚さが極端に低いことが一目瞭然⇒今後の行政の断熱強化施策にも活用されることを期待している 。